SNS利用時間の増加と子どものメンタル不調に関する因果関係を示す論文は複数存在する。
12~15歳の青少年約7,000人を対象とした米国の大規模縦断調査
SNSを1日3時間以上利用する群で、うつ症状や自傷傾向のリスクが2倍以上になるという有意な傾向が明らかとなっています。これはSNS利用が多いほどメンタルヘルス悪化に“先行”するリスクが示唆された点で、単なる「関連」だけでなく「因果的関係」を示そうとする内容。
また、英ランカスター大学のシステマティックレビューや、米国JAMA Psychiatry誌に掲載された10万人規模の追跡調査論文でも、SNS利用時間の多さがメンタル不調(不安・うつ・睡眠障害)発症リスクの拡大に寄与している、と結論付けられている。これらは利用時間がメンタルの悪化を引き起こす一因であることが強調されており、単なる逆相関の可能性だけでなく、一方向の因果関係が示唆されています。
従って、SNS利用時間の増加がメンタル不調の発生・悪化に「因果的」に関連するという論文は、国際的にもエビデンスとして認められつつあります。対策としては利用時間の制限、利用内容のモニタリング、適切なサポート体制の整備が有効とされています。
こうした研究は、SNSの長時間利用がうつ病や不安障害、睡眠障害のリスクを高めることを示しており、時間の経過とともにSNS利用がメンタル不調の先行要因となりうることを支持しています。
JAMA Psychiatryなどの権威ある医学誌で発表された大規模研究では、SNS利用が精神的健康障害の発症に寄与する因果性を示す証拠が示されている。
これらの論文を通じて、過剰なSNS利用がメンタルヘルス悪化の一因であることがエビデンスとして認められており、SNS利用時間の制限やメンタルヘルスの早期介入が推奨されている。具体的な論文例を知りたい場合は、「JAMA Psychiatry SNS use longitudinal study」や「Lancet systematic review social media mental health youth」で検索。
スマホと学力(成績)の関係を調べたデータから読み解く、子ども …
研究者が思わずゾッとした「子どものスマホ使用時間と偏差値の …
年齢別にみたSNS(スマホ含む)利用時間と学力への影響についてのデータは以下の通り。
小学生・中学生(例:仙台市教育委員会調査)
- 7万人規模の調査で、スマホ利用時間が1時間未満であれば学力に大きな悪影響はなく、むしろゼロ利用より若干高い成績傾向が見られた。
- しかし、1日2時間以上のスマホ利用は学力低下と明確に関連し、とくに4時間以上利用すると、勉強時間が少ない子よりも学力が低くなる傾向だった。
- LINEの利用時間の増加も顕著に学力低下と結びつき、特に1時間未満の利用でも悪影響が認められ、長期間の利用歴があると使用をやめても回復しにくいケースがあった。digitaldetox+2
高校生・大学生
- 大学生を対象にした調査では、LINE、Twitter、YouTubeの利用が学業成績に負の影響を与え、利用時間が増えるほど試験成績が悪化することが示された。
- 特にSNS利用により集中力散漫となり、勉強時間の減少が主な原因とされている。ssi+1
全体の傾向と注意点
- 年齢が上がるにつれSNS利用率は増えるが、学力低下との関連がやや強まる傾向。
- 低〜中学年までは適度なスマホ利用が成績に悪影響を及ぼすわけではなく、一方で過度な利用時間はどの年齢層でも学力低下に結びつく。
- LINEのような即時コミュニケーションアプリの使用は通知による集中力低下を引き起こしやすいことが影響している。e-adesso+2
以上のように、子どもの年齢により影響の度合いや特徴は異なるものの、特に1日1~2時間を超えるSNS・スマホ利用は学力低下に関係し、利用時間や使い方の管理が重要といえる。
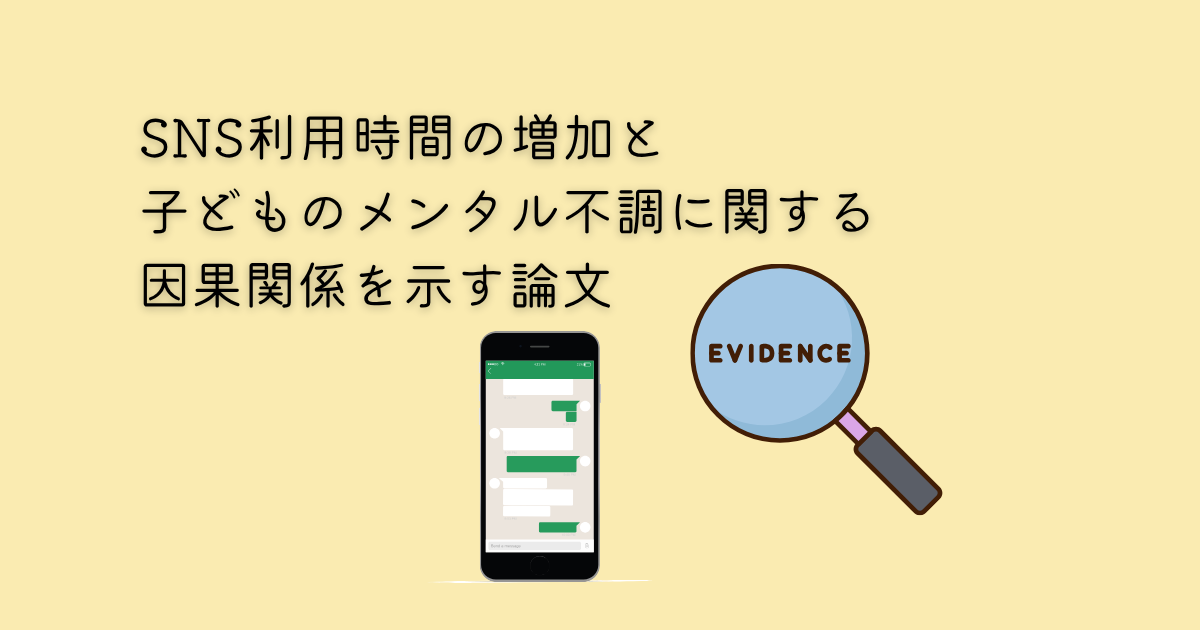
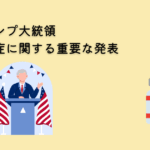

コメント