幼児期のスマホ・ゲーム依存を防ぐ理由
— スティーブ・ジョブズの考え方と、幼稚園からの具体的提案 —
アップル創業者のスティーブ・ジョブズは、自分の子どもにテクノロジー使用を厳しく制限していたことで知られています。世界最先端のITを創った本人が、なぜ家庭では制限したのか。そこには、幼児期の発達にとって「何を優先するか」という明確な視点がありました。彼はテクノロジーが子どもの好奇心を狭め、創造性や人間関係を築く力を奪う可能性を危惧していました。臼井幼稚園でも園だよりなどでお伝えしてきているように、同じ考えに立ち、子どもたちが今、その年齢に必要な遊びを中心にカリキュラムを組み立て、子どもが心身ともに健康に成長していけるように考えています。
幼児期に大切なこと
- 幼児期は「人との関わり・身体遊び・ごっこ/制作」など五感と想像力を使う時間がとても大切。
- 長時間の受動的な視聴や反復的ゲームは、睡眠・感情調整能力・集中力に影響しやすい。
- 家庭のルールと一貫性が最重要。親子で一緒につくるルール・ルールの見える化・親御さんが一緒に視聴することも大事。
ジョブズが「制限」したわけ
ジョブズはテクノロジーを否定したのではなく、使い方のバランスを重視しました。幼児期は特に、
- 人間関係の土台づくり(目を合わせる・順番を待つ・感情を言葉にする)
- 身体と感覚の統合(走る・つくる・触る・音や匂いを感じる)
- 想像力とごっこ遊び(役割交替・物語をつくる)
こうした経験は画面では代わりにならないため、家ではあえてスクリーンタイムを絞り「実体験の密度」を上げる戦略をとったと考えられます。
幼児発達の視点:長時間画面を見続けることによる主なリスク
- 睡眠の質低下:就寝前の刺激・光で寝つきが悪くなり、翌日の機嫌や集中に影響。
- 感情調整の難しさ:強い刺激への慣れで「待つ」「あきらめる」が育ちにくい。
- 言語・対話の機会が減る:やりとりの回数が減ると語彙や表現の伸びが鈍化。
- 身体活動の減少:粗大運動・微細運動の経験が不足しやすい。
専門機関のガイドラインでも、未就学児の画面時間は高品質の内容を保護者と一緒に短時間という原則が示されています(例:2–5歳は目安として1日1時間程度を上限)。
家庭で今日からできる「3つの基本ルール」
- 時間:「1日に視聴する時間を決めること」と「就寝前1時間は見ない」をセットで管理。タイマーや砂時計で見える化する。
- 場所:食卓・寝室は見せない。リビングなど親の目が届く場所で。
- 内容:共視聴(親子で一緒に見る)を基本に、年齢に合った高品質コンテンツを選ぶ。見終わったら「何が面白かった?」「次はどうする?」と対話で締める。
ルール掲示の例(印刷して冷蔵庫にどうぞ)
- ①見る前に決める(時間・場所・内容)
- ②タイマーが鳴ったら終了(延長は翌日の楽しみ)
- ③寝る前は絵本とお話(画面は使わない)
「やめる」だけにしない:代替案で「やめられた」成功体験を増やす
スクリーン時間を減らすほど、代わりに何をするかが重要です。
- 体育あそび:追いかけっこ、ボール運動、平均台
- 制作・感覚遊び:粘土・折り紙・段ボール工作・砂水あそび
- ごっこ・言葉:人形・ままごと・絵本の読み合い・ことば遊び
ご家庭でも、「先に遊び→あとで少し画面」の順番にすると切り替えが楽になります。
臼井幼稚園からのお願いとサポート
- 就寝時刻・朝の起床時刻を安定させましょう(睡眠が最優先の学習です)。
- 「うまくいった工夫」をぜひ教えてください。園でも皆さんにお知らせします。
臼井幼稚園はテクノロジーの排除ではなく、健やかな使い方を一緒に育てたいと考えています。
よくある質問
Q1. 完全に禁止すべきですか?
いいえ。年齢に合う内容を短時間・共視聴で取り入れるのは可能です。大切なのは睡眠・食事・外遊び・対話が先に満たされていること。
Q2. ゲームの約束を守れません。
「開始前に約束→タイマー→振り返り」をルーティン化しましょう。やめる合図(タイマー・BGMの終わり)を視覚・聴覚でセットに。延長は翌日の楽しみへ。
Q3. 教育アプリなら長くてもOK?
内容が良くても長時間はおすすめできません。。活動のバランス(身体・対話・創造)を崩さないことが最優先です。
Q4. 兄弟で時間差があると喧嘩に…
同時スタート・同時終了で管理し、終わったら共同の遊びに誘導すると切替がスムーズです。
ダイヤモンドオンラインで、このテーマでコラムがありましたので、幼児期に置き換えて記事にしてみました。
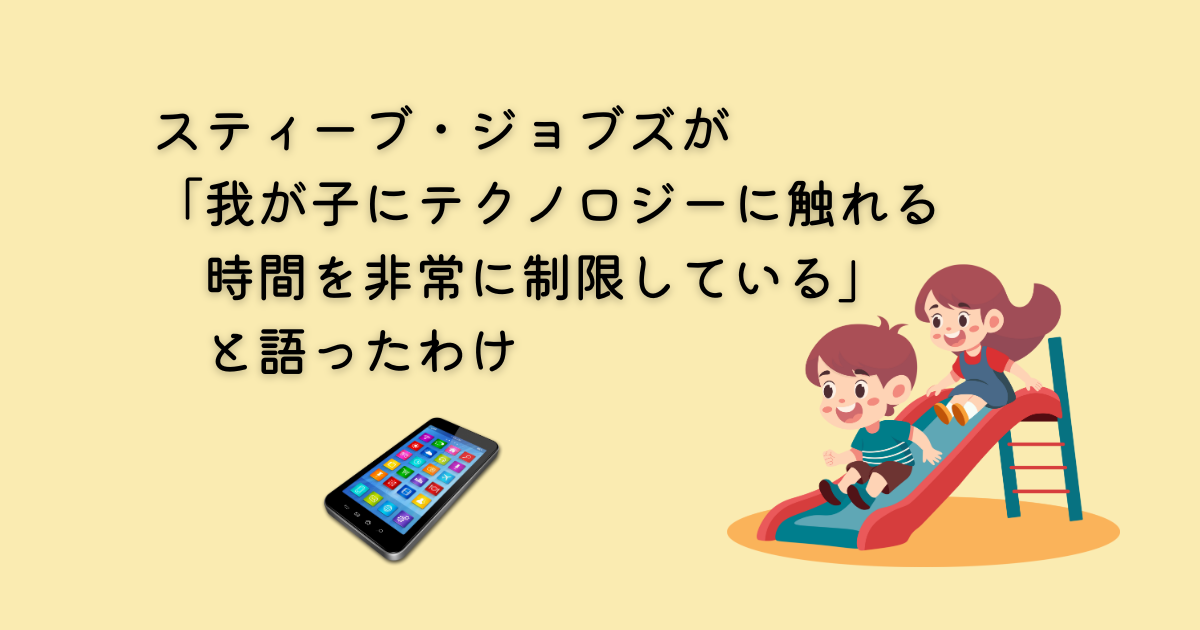
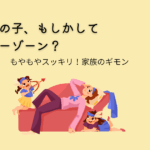
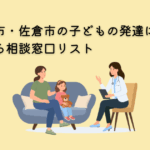
コメント